 Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫
Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫
 (イネスの涙の館のコンブラ6)
(イネスの涙の館のコンブラ6)
Portugal Photo Gallery --- Coimbra 6
![]()
≪1≫ コインブラ Coimbra ≪5月5日 夕方 郊外の市場≫
日曜日の夕方、コインブラの少し郊外にある広場では、露天市場が開催されていた。
西からの光を浴びたサント・アントニオ教会前の広場である。
 小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!
小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります! 
コインブラ214 コインブラA駅 |
コインブラ215 ポルタジェン広場 |
コインブラ216 モンデゴ川対岸 |
コインブラ217 コインブラの次の廃墟の駅 |
コインブラ218 サント・アントニオ教会 |
コインブラ219 サント・アントニオ教会の門 |
コインブラ220 露天市場 |
コインブラ221 広場の電飾 |
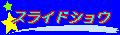 ≪コインブラ6≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!
≪コインブラ6≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!
![]()
≪2≫ コインブラ Coimbra ≪5月6日 小雨のコインブラ≫
ケイマ・ダス・フィタスのコインブラ大学の卒業パレードの翌日は、小雨がぱらつく日であった。
こんな日は、修道院、カテドラル、博物館などを見学することにした。
サンタ・クルス修道院 Mosteiro de Santa Cruz、新サンタ・クララ修道院 Convento de Santa Clara-Nova、
旧カテドラル Se Velha、涙の館 Quinta das Lagrimasなど、訪問した。
画像が多いので特集版も作りましたので、ぜひ、ごらんください。
 小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!
小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります! 
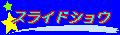 ≪コインブラ6≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!
≪コインブラ6≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!
![]()
 特集版・『涙の館 Quinta das Lagrimas』 こちらからどうぞ
特集版・『涙の館 Quinta das Lagrimas』 こちらからどうぞ
 特集版・『旧カテドラル&ミニ・ポルトガル』 こちらからどうぞ
特集版・『旧カテドラル&ミニ・ポルトガル』 こちらからどうぞ
![]()
 コインブラ6の説明
コインブラ6の説明

|
|
政治のリスボン、商業のポルトに次ぐポルトガル第3の都市コインブラは、文化の中心である。
丘の上の大学を中心に広がる。人口10万人ほどの小さな町だが、ポルトガルの歴史の中で果たした役割は大きい。
多くの政治家や文化人たちを世に送ったコインブラ大学は1290年にディニス王によって創設された。 |
![]()
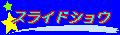 ≪コインブラ6≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!
≪コインブラ6≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!
![]()
|
「ポー君の旅日記」 ☆ イネスの涙の館のコインブラ6 ☆ 〔 文・杉澤理史 〕 ≪2013紀行文・10≫ 《もったいない》 「けいの豆日記ノート」 《サンタ・クララ橋を渡る》 「けいの豆日記ノート」 《ふたつのイザベル王妃像》 ・・・・ここで、簡素に『サンタ・イザベル物語』をご覧ください。・・・・ エストレモスのイザベル王妃像とコインブラのイザベル王妃像には違いがあった。それは手の位置である。
エストレモス像は下げた両手を開いた掌には薔薇の花々が、コインブラ像の右手は下に左手は胸にある。
13世紀と17世紀の違い、造り手の勝手であろうか。でも13世紀像の方が、おいらはシンプルで気品があって好きだった。
新サンタ・クララ修道院の中に入った。外観とは違い、教会内部は見事だ。心が安らんだ。重厚な教会はバロック様式である。
慈悲深かったイザベル王妃を愛しみ、銀製の棺にイザベルは眠っていた。今まで見た棺の中で一番美しく重厚に見えた。 「けいの豆日記ノート」 《10年振りのキンタ・ダス・ラグリマス》 「けいの豆日記ノート」 《イネス・デ・カストロ嬢に会う》 「けいの豆日記ノート」 《ティータイムならサンタ・クルス・カフェ》 「けいの豆日記ノート」 小雨の中をコピンブラでは老舗のホテル・アストリアに帰った。 途中の酒店で、帆船マークのカティー・サークを1本買った。40年以上も飲み続けているウイスキーだった。 オンザロックの水割りで飲みたかったが、ここはポルトガル。水は買ってきたが、氷は売ってない。 カウンターに行って、氷を分けてもらっても、その氷は水道水かも知れぬ。三つ星ホテルだと信じ、氷を分けてもらう。 カティー・サークのオンザロックの水割りを飲んだ。8日ぶりであった。 *「地球の歩き方」参照*
終わりまで、ポルトガル旅日記を読んでくださり、ありがとうございます。 |
≪ポルトガル写真集&紀行文・2013年版≫ バックナンバー&予定は、こちらからどうぞ・・・
2013−1話 Lisboa 13 |
2013−2話 Cascais 3 |
2013−3話 Nazare 2 |
2013−4話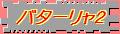 Batalha 2 |
2013−5話 Alcobaca 2 |
2013−6話 Caldas da Rainha2 |
2013−7話 Nazare 3 |
2013−8話 Porto de Mos & Ciria |
2013−9話 Coimbra 5 |
2013−10話 Coimbra 6 |
2013−11話 Visau 2 |
2013−12話 Porto 12 |
2013−13話 Barcelos 2 |
2013−14話 Gumaraes 2 |
2013−15話 Ponte de Lima & Lindozo |
2013−16話 Porto 13 |
2013−17話 Porto 14 |
2013−18話 Queluz 2 |
≪ポルトガル写真集&紀行文・2012年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・
2012−1話 Lisboa 10 |
2012−2話 Santarem |
2012−3話 Entroncamnto |
2012−4話 Tomar 2 |
2012−5話 Tomar 3 |
2012−6話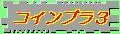 Coimbra 3 |
2012−7話 Cantanhede & anca |
2012−8話 Piodao |
2012−9話 Coimbra 4 |
2012−10話 Penela |
2012−11話 Azaruja&Evoramonte |
2012−12話 Elvas 2 |
2012−13話 Elvas 3 & Badajoz |
2012−14話 Estremoz 2 |
2012−15話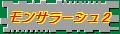 Monsaraz 2 |
2012−16話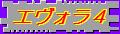 Evora 4 |
2012−17話 Evora 5 |
2012−18話 Lisboa11 & Cacihas2 |
2012−19話 Lisboa 12 |
2012−20話 Mafra 3 & Ericeira 2 |
≪ポルトガル写真集&紀行文・2008年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・
2008−1話 Lisboa 5 |
2008−2話 Cascais 2 |
2008−3話 Estoril 2 |
2008−4話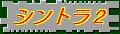 Sintra 2 |
2008−5話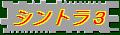 Sintra 3 |
2008−6話 Lisboa 6 |
2008−7話 Portalegre |
2008−8話 Castelo de Vide |
2008−9話 Portalegre 2 |
2008−10話 Portalegre 3 |
2008−11話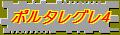 Portalegre 4 |
2008−12話 Mrvao |
2008−13話 Lisboa 7 |
2008−14話 Lisboa 8 |
2008−15話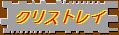 Cristo Rei |
2008−16話 Cacihas |
2008−17話 Nogueira Azeitao |
2008−18話 Fresca Azeitao |
2008−19話 Evora 2 |
2008−20話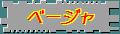 Beja |
2008−21話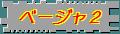 Beja 2 |
2008−22話 Serpa |
2008−23話 Vila Vicosa |
2008−24話 Borba |
2008−25話 Redondo |
2008−26話 Evora 3 |
2008−27話 Arraiolos 2 |
2008−28話 porto 8 |
2008−29話 Aveiro 2 |
2008−30話 Costa Nova |
2008−31話 Braga 2 |
2008−32話 porto 9 |
2008−33話 porto 10 |
2008−34話 porto 11 |
2008−35話 Lisboa 9 |
☆ コインブラ Coimbra シリーズです ☆
コインブラ1
・コインブラ2
・コインブラ3
・コインブラ4
・コインブラ5
・コインブラ6








































 特集版・『新サンタ・クララ修道院』 こちらからどうぞ
特集版・『新サンタ・クララ修道院』 こちらからどうぞ 特集版・『サンタ・クルス修道院』 こちらからどうぞ
特集版・『サンタ・クルス修道院』 こちらからどうぞ



