|
                        
「ポー君の旅日記」 ☆ 幼稚園のカンタニェデ&洗濯女のアンサー ☆ 〔 文・杉澤理史 〕
≪2012紀行文・7≫
=== 第三章●コインブラ起点の旅 === 幼稚園訪問のカンタニェデ&洗濯女のアンサー
《KIMIKOさん宅の朝》
ぐっすり眠ってしまった。毎朝6時前には目覚めるのに、7時であった。
原因は心地よさだった。
昨夜は部屋付きの清潔なバスに首まで浸かり、慣例のケチケチ旅でこんな贅沢をしていていいのだろうかと、至福に酔った。
そして、ベッドから斜めの天井にある大きな天窓越しに、夜空に輝く星を眺めながら寝入ってしまった。
身支度を整えテラスに出る。眼下に、5月25日(金)の大学の街コインブラの朝が、大パノラマで広がっている。
背筋を伸ばし、息を鼻から肺の中に目一杯吸い込み、唇をすぼめ、その隙間から長くゆっくり吐きだす。
それを10回繰り返すのがポーの日課である。
これをしないと、一日が始まらない。大袈裟ではなくその日の調子が判る。自己流健康チェックだ。
カメラのシャター音が、南に面した曲線的な広いテラスの端から聞こえた。
『KIMIKOさんと話していたら12時を過ぎていたよ。でも、楽しかった。
久しぶりに一杯話せた。寝たのは1時過ぎかな〜』と、相棒。
昨夜は話が弾んだようだった。
昨日は、世界遺産・キリスト修道院があるトマールの街を早朝から歩き回り、万歩計も2万歩に18歩足りなかったが、よく歩いたものだ。
そのためか、歳のせいか、風呂にゆっくり浸(つ)かりたく、2人の会話から抜け出したのは10時頃である。
大きなテーブルに朝食が用意されていた。ふたりの子供たちはテレビの漫画を見ている。
こちらでも朝から子供向け番組が欠かせないようだ。香りが気をそそる煎りたてのコーヒーが待っていた。
ペーパードリップ式の手間のかかる美味しいコーヒーであった。
忙しい朝の時間にも関わらず、KIMIKOさんの心こもったおもてなしが何よりありがたく嬉しかった。
「けいの豆日記ノート」
昨晩は、話していて遅くまで起きていたのに、私が起きる前に、ちゃんと朝食の支度ができていた。
睡眠時間、きっと少なかったに違いない。
朝が苦手な私では、できないなあと思った。
おいしいコーヒーにミルクをたっぷりといれて、お代わりもした。
朝から、たっぷりと食べて、お腹も心も満杯であった。
《いざ、幼稚園に》
KIMIKOさんが苦労し段取りしてくれた幼稚園に向かった。
[コインブラ]の自宅から15キロメートル北にある[カンタニェデ]まで、KIMIKOさんの運転だ。
8時50分に出発した。6歳の男の子と2歳半の女の子もその幼稚園に毎日、母親の運転で通っているという。
母親の勤め先でもあった。助手席に相棒、後ろの席に子供用の安全シートふたつに挟まれポーが座る。
窮屈だが、すんなりポーは収まる。昨日降りた国鉄コインブラB駅までは渋滞であったが、相変わらず人びとで賑わう駅を右手に見ながら北上した。
右から左から子供たちのかん高い質問攻めの声がポーを射る。
ポルトガル語を解せないポーは、Sim、Sim(はい、はい)と答える。子供たちは不満顔だ。
ポーだって黙ってはいない。日本語を子供たちに浴びせる。ふたりは大人びた顔で、ニッカと笑う。
子供たちには、3か月前に会っていた。KIMIKOさんが実家のある常滑市に、妹の結婚式のために里帰りしていた時だ。
だから、顔見知りである。そこで、ポーは瞬時に考え、この窮地を打破するにはこれしかないとじゃんけんでの「あっち向け、ホイ!」で難を逃れる。
キャー!キャー!とポーに負けた子供たちは悔しさの歓声を上げる。前の席からは女性陣の笑い声が弾ける。
それでいい。笑顔の空気が流れれば・・・だ。
曇り空を割って、陽射しが輝いて来た。今日も晴れるに違いない。だって晴れ男、ポーがいるのだから。
幼稚園のある[カンタニェデ]の街は、西に向かって40キロメートル先は大西洋。北に向かえば、[アヴェイロ]。
その先はポルトガル第2都市[ポルト]だ。
アヴェイロは、入り組んだリア(潟)が内陸に食い込んだ、自然の良港として栄えてきた街だ。
中央運河には色鮮やかなモリセイロという船が観光客に人気だ。
ポルトは、スペインから流れるドウロ川河口にあり、上流のブドウ産地で絞った原液をワイナリーで生産する、ポートワインで名高い北の都である。
(ちなみに大学の街コインブラは、南にある首都リスボンから列車で2時間〜2時間半。
北の第2都市ポルトまで列車で1時間半〜2時間の位置にある)
「けいの豆日記ノート」
カンタニェデという地名は、今回のポルトガルの旅の計画をする際に、はじめて知った町である。
グーグル地図でみると、けっこう大きな町であることがわかる。
コインブラからかなり離れていて、毎日、車で通うのは、たいへんだと思った。
郊外だと、交通の便が悪くなるので、どうしても車が必要になる。
運転することは、生活の上で必需なのだと思う。
(今どき珍しく、だれかは、免許がない・・・のであるが・・・)
《念願の幼稚園に着く》
幼稚園は、カンタニェデの街から更に10キロメートルほどの郊外にあった。田園地帯にある田舎町だ。
広い通りには、太陽で輝く2階建の真っ白い壁にオレンジの屋根が連なっている。青空をさえぎる高いビルもない。
たまに通る車は、荷台に農器具を積んだ小型トラックだ。
それに、道を歩く人影もなく、まことに長閑で静かな明るい田舎町であった。
広い道の四差路には信号もなく、横断歩道の白いマークもない角地に幼稚園はあった。
広い敷地の中に2階建の白い壁とオレンジ屋根の清楚な幼稚園である。
隣にある白い壁にオレンジ屋根の小さな教会も、町の中に溶け込んでいた。
この環境から考えても人口もそう多くなさそうだし、園児は15人か20人もいればとポーは思う。
園長室で、園長さんに紹介され、撮影をさせていただくことに感謝の念を相棒が伝えた。
勿論、KIMIKOさんのお助けで伝えてもらう。
気品のある風格に、笑顔が似合う園長さんであった。
KIMIKOがお世話になっていますと、相棒の手を握った。
園長さんはKIMIKOさんの義母だと、ポーは初めて悟った。
隣のお髭の似合う大柄な老紳士は義父だった。
今回の幼稚園撮影訪問は相棒の要望を受け、KIMIKOさんの優しさが受けとめ進めた企画だったので、ポーは蚊帳の外であった。
旅のスケジュールを立てた相棒に幼稚園のことを聞こうとすると、お楽しみ、お楽しみとはぐらかされた。
この撮影プランが実現するまでには、いろいろな苦労があったようだ。
「けいの豆日記ノート」
念願であった、幼稚園の撮影がかなうと思うとワクワクしていた。
今まで、ポルトガルの各地で、学校や幼稚園は見てきた。
正確に言うと、外観だけ見てきたのである。
中には、入れてもらえなかった。
登校、下校の時間以外は、玄関の扉は、しっかりと鍵がかけられていた。
部外者は、入れないようになっている。
中の子供たちも外には、出れないようになっている。
大事な子供たちの安全を守るうえで、セキュリティは、しっかりしないといけないのであろう。
なので、塀の外から撮るか、登下校のときに撮るかしかなかった。
子供たちは、写真好きなので、見つけると寄ってくるのだが、
塀の外からだとオリに入っている子供のようになってしまうのである。
《夢の実現を撮る》
まず3つの広い部屋を、ひとつずつ案内された。1歳児、2歳児、そして3〜5歳児、合わせて40人ほどの園児がいた。
想像していたより園児は多かった。園児は緑の襟に、青いチェック柄のおそろいの服を着ていた。
案内してくれた後、園長さんは微笑んで言った。
自由に部屋に入り、自由に撮ってください。
しかし、首に下げた手作りの紙メタルを下げている子は、写真展での発表はお許しください。
おやごさんからの撮影許可がとれませんでした。
そんなわけで気を使う撮影になるでしょうが、楽しい撮影になるよう祈っていますよ KEIKOさん、と申し訳なさそうに言う。
相棒は『オブリガーダ!』と園長さんに頭を下げ、『ありがとう!』とKIMIKOさんの手を握った。
首に手作りの紙メタルを下げている園児は13人ほどいる。集合的写真は無理かもしれない。
1人写真だと記念写真になりかねない。
相棒の腕の見せ所だ。心配することはない、あったかい写真を撮るに違いないからだ。
今まで学校や幼稚園の子供たちを撮りたくても、校内や園内で子供たちを自由に撮影することは不可能であった。
KIMIKOさんが、園長を口説き、仲間を口説き、子供たちの親を口説き、相棒の夢を可能にするまでには彼女のどれほどの苦労があったか計り知れない。
KIMIKOさんが与えてくれた友情の、夢の実現であった。
子供たちは自然体で、無邪気に日本から来たカメラマンに向き合ってくれた。警戒心を解きほぐすには時間はいらなかった。
相棒は、母親になっていた。心のひだを解きほぐす術を、心得ていた。二人の子供がいる母親でもある相棒。
その母親の重みが糧(かて)である。
部屋を渡り歩き、自由に撮影することの嬉しさが、撮影する相棒の動きから伝わって来た。
KIMIKOさんが与えてくれた憧れの撮影現場を満喫し、感謝して楽しめばいいのだ。
ワンカット、ワンカットの映像を、感謝をこめてシャッターを切る。
それが、KIMIKOさんへの感謝のひと押しなのだ。
相棒の取材する後ろ姿から、ポーはひと押しひと押しのシャッター音に納得し、心地よく感じていたのだった。
「けいの豆日記ノート」
子供たちの写真を撮る場合、そこで働いている保母さんでも、親の許可が必要だと聞いた。
いろいろなイベントがあるごとに必要らしい。
犯罪などもあり、子供たちの写真には、気を使っている。
写真展の展示写真だけならOKで、ネットはダメだという親もいるし、全面的にダメという親もいる。
いくら保母さんの知人の写真家だといっても、信用できるという保証はないのである。
わかるように印を作ってくれたが、隠れて見えなくなったりする。
数人の写真を撮ろうとすると、その中にダメな子が入っていたりする。
考えていると撮れないので、とりあえず、好きなように写真を撮って、後から避けてもらうことにした。
3分の1は、使えない写真かもしれない。
《給食時間》
食堂では、優しい瞳のおばさん一人が昼食をつくっていた。
大きなお皿に盛りつけられているのは、オリーブ炒めのお米(具が入っていないが炒飯ぽい)にサラダ、それに豚のソティーだ。
ソティーは、細かく切った一口で食べられる大きさで園児の年齢別に配慮してある。
カウンターに並べられた皿を園児一人ひとりが取りに行き、テーブルに着く。祈りを上げ、嬉しそうに食べる様子を相棒が切り撮っていた。
昼食の食材費は、国から援助があるという。また、入園費は毎月40ユーロ〜60ユーロ(4000円〜6000円)だと聞く。
身体の大きな7歳以上の子どもたちが食堂に入って来た。近くにある小学生だとKIMIKOさんが言う。
この幼稚園の卒園生で、親が働いていて家に昼食で帰れない子は、ここで食べられるのだ。
肉も細かく切ってなく、1枚そのままの大きさであった。
我らのために小学生と同じ昼食が用意されていた。テーブルに園長さん,KIMIKOさん、相棒にポー。
ポーはぺろりと平らげた。米の炒めものは久しぶり。驚くほどの美味さはない。
でも、炒飯ではないが皿の半分を占める米の存在が嬉しかった。
「けいの豆日記ノート」
ポルトガルの学校では、基本的には、給食はない。
家に帰って食べるようである。
なので、昼休みの時間が長いのである。
この幼稚園では、給食があった。
幼稚園というより、保育園といったほうがいいのかもしれない。
働くお母さんの子供たちを預かっているのである。
給食を作っている場面をはじめてみることができた。
給食センターとかからの取り寄せでなく、全部、この幼稚園で作っているのである。
だれが、どの皿を食べるのか、ちゃんと把握していて、量の加減とか、肉の切り方とか変えているのである。
子供一人ひとりにあわせた食事は、すてきであった。
《園長さんの家》
昼食後、園長さんがご自宅に招待してくれた。自宅訪問の撮影は、望んでもかなり難しい。
一介(いっかい)の旅人にとっては、不可能に近い。それが、実現したのだ。これもKIMIKOさんの配慮かもしれない。
車で、15分ほど走った。すれ違う車がない。
でも、カンタニェデの郊外は、広い敷地に素敵な一軒家が次々と車窓を飾る高級住宅地に思えた。
住宅地を抜けると、ひときわ陽射しを浴びた田園風景が広がる。
大きな木が茂る中に、白い壁の3階建の家が見えた。園長さんの住まいであった。車から降りて気付く。
壁は薄いピンク色だった。陽射しの強さで白く見えたようだ。
先に帰っていたハンチングに白いお髭のご主人が迎えてくれ、庭を案内してくれた。わっ、お〜ゥ!と、思わずポーは声を発した。
自宅の背後は庭というより大地である。遥か先まで畑が連なり、葡萄畑が広がっていた。
農機具置き場の納屋で、年代物の磨かれたドイツ車フォルクスワーゲンを発見。右ハンドルの、若草色のボディが美しい。
通称カブトムシと呼ばれた小型自動車だ。1938年〜2003年まで生産されていた。
ポーが若い頃憧れた車だった高級車だ、欲しくても、手も足も出なかった。
その車が無造作に農機具の間に収まっている。バンパーの作りからすると、スマートさに欠けた頑強的デザインである。
これは逸品だ。何年物か後で聞こうとポーは思う。
納屋の隣りでは、豚や七面鳥、アヒル、ニワトリを飼っている。売るためでなく、自給自足の家族の一員だ。
その小屋の周りには開花間近の紫陽花が繁り、大きな葉に5センチメートルもあるカタツムリがいた。
日本で発見したなら相棒は必ず持って帰るに違いない。
と言うのも、JR車中で偶然見つけた雨蛙を、踏みつけられたら可愛そうと持ち帰り、もう3年も水槽で飼っているほどだ。
動く生きた餌しか食べない雨蛙のために、四苦八苦し、今はコオロギの生まれたてを通販で買って与えている。
3年飼っていても、一度も鳴かない〈JRケロちゃん〉。メスなのかも知れない・・・。
家の中に案内された。玄関を入った所に医務室がある。歯を治療するとても古い形の器具がおいてあった。
40年ほど前の日本製だという。白い髭のご主人は歯医者だった。81歳の今は、予約患者だけを診ているそうだ。
園長さんは何処を撮ってもいいですよ、と言ってくれた。どの部屋も素敵な調度品が整えられ、裕福さが伝わって来た。
磨き抜かれた木製手すりに触れながら2階に行く白い壁にも、3階に上る階段の壁にも、モノクロ写真の人物が額に収まって微笑む。
代々受け継がれてきた家族写真である。
若い時の園長さんは、ブロマイド写真のようだった。
帰り際に収穫したばかりの、山盛りになった空豆の太った莢(さや)を見つけた。ポーが大好きな豆だ。
でも、値段が高いためなかなか口に入らない。
お髭のご主人に20粒ほど頂けないかと言うと、大きな袋に莢に収まった空豆を100個ほどもくれた。
日本のスーパーマーケットで買えば3000円はする量だった。
今夜はKIMIKOさん宅で腕をふるってポーの空豆料理をみなにご馳走しよう。
そうだ、空豆で一杯飲もう!とポーの心は嬉しさで揺らいだ。また、
納屋の奥の地下室からラベルが貼ってないワイン瓶を4本持って来てくれた。
自家製赤ワインで、自分たちが飲む秘蔵のワインだと言う。
ポーは嬉しさで舞いあがり、フォルクスワーゲンのことをすっかり忘れていたのだった。
「けいの豆日記ノート」
昼休みに幼稚園に関係している人の自宅も見せてもらった。
個人の家は、なかなか撮影できない場所である。
遠く日本から来たのだから、特別に見せてくれたのだと思う。
土地も広く、大きな家は、とてもきれいだった。
自分の小さい家の何倍もあるすてきな家であった。
日頃の管理や掃除などもたいへんだと思う。
幼稚園の撮影を終えて、園長先生の自宅に向かっていた。
周りを畑に囲まれた家の敷地はどれくらいあるのだろうか。
ピンクの壁のすてきな家は、旅人のペンサオン(宿泊できる家)にもなっているようである。
大きな家には、部屋がいっぱいで、伝統ある家具がなにげなく置いてあった。
こんなペンサオンに泊まりたいなあと思う。
交通の便が悪いので、足のない私には、ムリかもしれないが、
バイクやレンタカーなどで移動する人たちには、いいペンサオンだと思う。
『カンタニェデの園長先生の家』の部屋や農園のようすはこちらからどうぞ!(連絡先の住所・電話番号の記載があります)
《ポルトガルの洗濯女》
お土産を沢山もらった園長さんの家からカンタニェデの中心地に向かう。
午後5時を過ぎていたが、まだ太陽は燦々(さんさん)と輝いている。
広場にある教会の前に騎馬姿の銅像がある。
持参の「ポ日小辞典」で大理石に書かれた文字を引くと〈故郷の解放者〉と読める。人も馬も繊細で力強い。
なかなかの出来栄えだ。下から見上げているので、青い空に浮かぶ銅像は作品としても見応えがあった。
カンタニェデ市はコインブラ郡の中でも観光客に人気で、学術博物館や化学博物館、マチャドデカストロ美術館を訪れる人で賑わうらしい。
時間も時間、KIMIKOさんが考えていてくれた帰り道の[アンサン Anca]という町に向かった。
アンサンに着いたのは午後6時。まだまだ陽射しは、有り余るほどあった。古い街並みだが水の音が聞こえてくる静けさがある。
KIMIKOさんの後をついて行くと、幾筋にも流れる水路があり、その先に石組の大きな水槽が見えた。昔から今日にまで受け継いできた洗濯場であった。
水浸(みずびた)しで絨毯を洗う女性、豊富な水量に流されないようにして衣類を洗う女性など、お年寄りから若い娘までが洗濯をしていた。
夕食前のひと仕事と言ったところか。
こちらの夕食は9時頃だ。
1952年にヒットした、シャンソン歌手のイヴェット・ジローが歌った「ポルトガルの洗濯女」が聞こえてきそうな雰囲気があった。
♪洗濯女を知ってるかい ポルトガルの洗濯女を とりわけセチュバル村の洗濯女を(セチュバル=セトゥーバル)
そこは洗い場というより 社交場のようだ・・・バシャバシャ精を出せば バシャバシャ今夜はよくねれる♪
「けいの豆日記ノート」
ポルトガルのいろいろな町で、洗濯場を見ることがある。
でも、壊れていたり、使われていなかったりで、実際に洗濯をしている光景は見たことがなかった。
自宅に洗濯機のない家はないだろうし、そのほうが作業も楽であるので、当たり前なのかと思っていた。
この町で実際に洗濯をしている現場を初めて見ることができた。
洗濯ができるということは、水がきれいな証拠である。
《空豆で乾杯》
KIMIKOさん家(ち)に着くと即、空豆の莢(さや)むきにポーは取り掛かる。午後8時を過ぎていた。
一つの莢から大きな空豆が3つ平均で出てきた。全部むけば300粒ほどにはなる。
50個むいたころから指の先が痛くなった。
空豆大好き人間と言えども、ひとりで100粒も食べられない。
莢付きでは保存も利かないから100個ほど全部むいて、それを保存する術を考える。
相棒は今日撮った写真の整理をしていた。幼稚園での写真はKIMIKOさんのパソコンに移す。
日本に帰ってから送るより今映像を渡しておけば彼女も紙メタルの子が映っているかチェックができるからだった。
しかし、幼稚園の分だけでも300カットはあるはずだ。
空豆を美味しく食べるには茹(ゆ)で加減次第だ。そこでポーは考えた。
大小の鍋を用意し、茹でたてそのまま食べる50粒を小さい鍋で塩ふたつかみ入れ、やや柔らかめに茹でる。
大鍋には250粒を塩やや多めで硬めに茹であげた。
このうち150粒は熱を冷ましてから冷凍し、残りの100粒は薄皮を取りバターで軽く炒めた。
午後9時。流れる雲が焼ける頃、今夜もコインブラの街を見下ろすテラスで夕食だ。
KIMIKOさんの今夜の手料理は、義母から頂いてきた生ハムとレタスのサラダ、それにいろいろな具が白いご飯に挟まれ層になっているご飯である。
差し詰め、具が混ざり合っていないが、炊き込み風ごはんだった。アイデア抜群、うまい。
日本に帰ったら98歳になる母に造ってやろうと思う。
さてさて宴の締めは、頂いてきた秘蔵の赤ワインと空豆で乾杯であった。
薄皮を指でつまむと緑鮮やかな空豆が口の中に飛び込む。ひょいひょいと10粒が消えていく。
ワインを一口飲む。バター炒めの空豆もスプーンですくってすいすい口の中。こんな贅沢はない。
二度とないかも知れない。空豆の食いっぷりに2人の女性はあきれ果てていた。
*「地球の歩き方」参照*
                        
終わりまで、ポルトガル旅日記を読んでくださり、ありがとうございます。
次回をお楽しみに・・・・・・・今回分は2013年 1月に掲載いたしました。
|
 Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫
Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫ (幼稚園のカンタニェデ&洗濯女のアンサー)
(幼稚園のカンタニェデ&洗濯女のアンサー) 小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!
小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります! 
![]()
![]()
![]()
 カンタニェデ&アンサーの説明 (写真の上をクリックすると大きな写真&コメントのページになります)
カンタニェデ&アンサーの説明 (写真の上をクリックすると大きな写真&コメントのページになります)


![]()














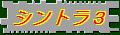














































































 『カンタニェデの園長先生の家』はこちらからどうぞ!
『カンタニェデの園長先生の家』はこちらからどうぞ!


